名勝 雙ヶ岡 (右京区御室双岡町)
春の陽気に誘われて雙ヶ岡(ならびがおか, 双ヶ岡, 双ヶ丘などとも表示される)に登ってみた。東麓の遊歩道「つれづれの道」沿いにある「はなみのひろば」では、元気な子供達が走り回っている。
【名勝 雙ヶ岡って?】

嵐電「御室仁和寺駅」のすぐ南側に位置し、南北に並ぶ三つの岡を総称して「雙ヶ岡」と呼ぶ。古生層の独立丘で、京都盆地における卓越した展望地点として昭和16年に国の名勝に指定されている。北から順に「一ノ丘」「二ノ丘」「三ノ丘」と並ぶが、遠くから望むとラクダの二つのコブのように見える。
[一ノ丘]
最も高い丘で標高116m。頂上付近には巨石を使用した両袖式の横穴式石室を有する円墳(直径44m, 高さ 8m弱) があり、右京近辺では太秦面影町の蛇塚古墳の石室に次ぐ大きさだという。昭和55年の発掘調査では、須恵器、土師器、金環、鉄製品、石棺の破片などが出土している。6世紀後半から7世紀前半にかけての築造と推定され、石室の開口部から嵯峨野地域が一望できることから秦氏の長の墓と考えられているようだ。
8m弱) があり、右京近辺では太秦面影町の蛇塚古墳の石室に次ぐ大きさだという。昭和55年の発掘調査では、須恵器、土師器、金環、鉄製品、石棺の破片などが出土している。6世紀後半から7世紀前半にかけての築造と推定され、石室の開口部から嵯峨野地域が一望できることから秦氏の長の墓と考えられているようだ。
一ノ丘の頂上からは、北に仁和寺と背後の成就山、西南方向には嵐山周辺を眺望することができる。また少し離れた所には「右大臣贈正二位 清原真人夏野公墓」と刻まれた立派な石柱が建立されている。清原夏野(782-837) は平安時代初期の貴族で、雙ヶ岡の南東にある法金剛院は、彼の山荘が「双丘寺」という寺院になったのを始まりとする。ただ一号墳の築造年から考えると、この円墳が夏野の墓とは言えないのでは…。中世、この辺りは天皇遊猟の地で、夏野も親しんだであろうことから建てられた碑なのかも。
[二ノ丘・三ノ丘]

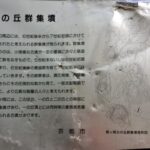 一ノ丘と二ノ丘の間の谷筋、二ノ丘と三ノ丘の間の谷筋には小型の円墳がいくつもあるらしいが、歩いているとただゴツゴツとした岩山が続くとしか思えない。二ノ丘(標高102m)の頂上には「とおみのひろば」と名付けられた開けた平地がある。ここからは、比叡山から大文字山へと続く東山連峰の稜線が眺められ、その麓には五山送り火の「法」が灯る松ヶ崎東山、北野天満宮の杜そして吉田山も見える。近くには妙心寺の甍の波が広がる。少し視線を南の方に向ければ京都タワーが目に入り、昔は碁盤の目の京の街が眼下に広がっていたのだろうと思うと感慨深い。
一ノ丘と二ノ丘の間の谷筋、二ノ丘と三ノ丘の間の谷筋には小型の円墳がいくつもあるらしいが、歩いているとただゴツゴツとした岩山が続くとしか思えない。二ノ丘(標高102m)の頂上には「とおみのひろば」と名付けられた開けた平地がある。ここからは、比叡山から大文字山へと続く東山連峰の稜線が眺められ、その麓には五山送り火の「法」が灯る松ヶ崎東山、北野天満宮の杜そして吉田山も見える。近くには妙心寺の甍の波が広がる。少し視線を南の方に向ければ京都タワーが目に入り、昔は碁盤の目の京の街が眼下に広がっていたのだろうと思うと感慨深い。
 二ノ丘から三ノ丘(標高78m)までの下りはすぐで、大きなまるで磐座(いわくら) のような大岩が印象的。岩の上では子供達が休憩中?三ノ丘から「つれづれの道」まではあっという間で、登り口のお地蔵さまに合掌。
二ノ丘から三ノ丘(標高78m)までの下りはすぐで、大きなまるで磐座(いわくら) のような大岩が印象的。岩の上では子供達が休憩中?三ノ丘から「つれづれの道」まではあっという間で、登り口のお地蔵さまに合掌。
ちぎりおく 花とならびの 岡のべに
あはれいくよの 春をすぐさむ (兼好法師集)
<参考資料>
・京都市情報館 記念物ガイド
・京都歴史散策マップ 3 太秦 双ヶ岡コース (京都市埋蔵文化財研究所)
・『平安京百景 : 京都平安京創生館展示図録』 京都市生涯学習振興財団, 2021
